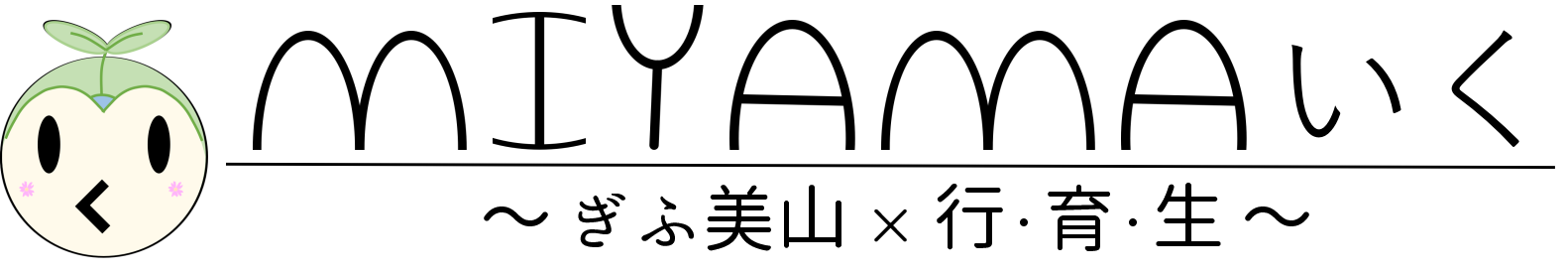私たちは 持続可能な社会へのヒントは 山里にこそあると信じています
現在、SDGsに代表されるように、世界規模で持続可能な社会への変革が叫ばれ、私たちは大きな転換点に立っています。
一方で、日本各地にある山間地域の山里に目を移すと…
人々の暮らしは、常に自然と共にあり、自然に適度に手を加えながら、災害から身を守ったり、食物を得たり、生業を営んだりしてきました。
自身や家族、仲間はもちろん、子孫のことも考えながら、代々守り継いできたことで、山林や河川に対して畏敬や畏怖が生まれ、数々の暮らしの仕組みや伝統文化、民話などが発展するとともに、独特で豊かな景観が育まれてきました。
また、多くの山里では自然の厳しさの面が強く出るため、人々が常に助け合いながら暮らす仕組みや文化が育まれています。
もちろん、現代のSDGsの考え方とは異なる部分もありますが、そういったものも含めて、ヒントとして集めていくことは、
持続可能な社会に貢献するためには有意義だと言えます。
私たち、MIYAMAいく は、
岐阜県山県市美山地域を中心に、以下の3つのことを大切にして活動しています。
美山 × 行
ぎふ美山に行く
美山地域に
行き来したくなる
きっかけづくり
<各種プログラムの企画運営>
美山 × 育
つながりを育む
美山地域の
自然・人・文化 の
つながりを知り 育みます
<調査研究・保全活動・再生活動>
美山 × 生
ともに生きる
つながりに加わり
自分自身と向き合い
地域に寄り添う
<情報発信・移住定住の促進>
美山 × 行 : ぎふ美山に 行く
ー 美山地域に行き来したくなるきっかけづくり ー

住民の方々や自然環境を最優先に、地域に寄り添いながら…
web上での投稿や、現地を案内する企画・運営をおこない、ぎふ美山の魅力を発信します。
現地を案内する際には、地域と来訪者のお互いにとって、より有意義な時間となるよう、
双方にできるかぎり寄り添います。
そうして、何度も通ったり、来られなくとも気にかけていただけるような人が少しでも増え、
さらには、地域の課題を深く知り、私たちとともに解決を目指して活動していただける、
そんな仲間が増えていくことを願っています。
美山 × 育 : つながりを 育む
ー 自然・人・文化 のつながりを知り 育む ー
1.つながりを 知る
私たちは移住者です。
ぎふ美山については、まだまだ知らないことばかりです。
だからこそ、できるところから、 自然・人・文化 について知るところから始めていきます。
地域で暮らし、つながりの輪に入ることで見えてくるものがあるかもしれません。
それ以外の部分では、私の専門領域でもある農村計画学や生態学の知見や経験を活かして、
人から聞いたり、文献を探して読み込んだり、現地を歩いたりして、調査・研究を進めます。

2.つながりを 守る
暮らしのなかや調査・研究を進めることで知ることができた 自然・人・文化 のつながりを
自身の暮らしはもちろん、積極的な働きかけをすることで、守っていきます。
具体的には…
今、良い状態のものは、よりよい状態で活用し続け、保全していく仕組みづくり・または既に仕組みがあれば引き継いでいきます。
既に劣化、または失われてしまっているものについては、できる限り再生できるような仕組みづくり
などをおこなっていきます。

3.つながりを伝える
一人の住民、一世帯の家族として、自然のプロとして…
自身が保全または再生に向けて実践していきながら、仲間を集めて活動の輪を広げていき、
未来へ ぎふ美山の魅力を引き継いでいくことに貢献していきます。

≪実績≫
○イワザクラについて
・定点観察におけるイワザクラの開花個体数調査
・イワザクラの採種、また播種からの栽培と栽培個体の生息地への移植(生息域外保全と保全的移植)、移植後のモニタリング
・イワザクラについて小学校等での授業に講師として参加(先代の講師の地元住民の方から引き継ぐ)
○森林整備について
・他団体とともに、居住地域の一部における森林の倒木の整理、間伐などの整備を実施。
・同林内の整備作業を体験型プログラムとして企画し、一般参加者を募って実施。
・同林内の整備で出た剪定枝等を活用しバードコールや小枝のボールペン、杉の葉のお香などをつくるワークショップを開催。
美山 × 生 : ともに生きる
ぎふ美山 の 人とつながり、伝統文化とつながり、自然とつながり…
つながりに加わることは、
繋がる相手を知り、尊重し、寄り添うことで初めて成し得ます。
自らの「らしさ」 や「 生き方」 と向き合うことも必要かもしれません。
私たちの周囲を見渡してみても、
ガラスや茶碗などの陶器は、元々は土や石。
プラスチックなどの化石燃料製品の大半も、元々は植物…
挙げればきりがありませんが、私たち人は、自然なくしてはいきていけません。
また、自然と関わり生きるためには、たくさんの人々と助け合う社会の中でしか生きられません。
ぎふ美山では、
人・文化・自然 の密接な関りがあり、集会や祭事、山林の整備活動など、
たくさんの地域の行事があります。
田舎暮らしはスローライフなどと言われたりすることもありますが、
私たちの山里の人々の印象は、真逆とも言えるもので、
目まぐるしく変化する自然や人との関りの中で、とても忙しなく暮らされています。
ただ、地域の皆さまは慣れているために、傍から見ると忙しなく見えないかもしれません。
住んで関わって初めて、わかることなのかもしれません。
余暇時間の最たるもののような井戸端会議であっても、田舎では大切。
ふとした時間に、どれだけ多くのことを学ばせていただいたかわかりませんし、
この時間に、互いの困っていることを伝えあって助け合ったりもできています。
(畑や山林の管理、道具の修理や貸し借り譲渡、祭事、人付き合い、暮らしのあれこれ…)
過去には、地域の行事や関りは、どこの地域でも当たり前にあったことですが、
社会の変化の影響もあり、近年は減少傾向にあります。
しがらみ と言われたりすることもありますが、
私たちは、人が自然と向き合い、暮らしを営むためには必要なことだと感じています。
また、今 の世の中だからこそ、注目を浴びているのかもしれません。
ぎふ美山の 人・文化・自然 とつながることは、
自分とはちがう、人・文化・自然に寄り添うことから始まります。
もしかしたら、これまでの自身の生き方を見つめなおしたり、
今後の生き方を考えるきっかけになるかもしれません。